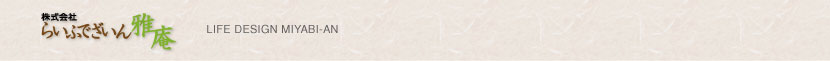退職給付会計
過去の企業会計では、将来支払う退職金・年金は、正式な債務としては認識されず、「隠れ債務」といわれていました。
会計のグローバル化という流れから、退職給付債務を、2001年3月期決算より年金や退職一時金といった退職給付債務の開示が義務づけられ、積立不足については退職給付引当金として貸借対照表に計上しなくてはならなくなりました。
新ルールでは、各従業員の残存勤務年数に応じて割引計算を行い、全従業員の合算をしたものを退職給付債務とします。
![]()
企業は剰余金等で、退職給付債務を積み立てきれれば問題はありません。
しかし、積立不足分は退職給付引当金を計上して賄わなければなりません。
(日本では、年金制度の多くが年金財政上の債務の評価を5.5%と比較的高い設定としていますが、会計上の割引率は現在の低金利状況を繁栄する必要があり、会計上の積立不足が発生してしまいます。)
この時多額の引当損が発生することが予想されるため、それを一度ではなく5年から15年の期間で、定額法で費用処理することとされました。
また、小規模企業(従業員数300人未満)の企業は簡便方を用いて退職給付債務を計算することができます。
法人税法で規定されている退職給与引当金は、期末時に全従業員が自己都合により退職した場合に支払う退職金額の20%を、平成15年からは積み立てることになっています。
退職給付会計と法人税法上の退職給与引当金とは、積み立てる割合が違います。
外部に拠出する掛金についても違いがあります。
退職給付会計では掛金について退職給付引当金を取り崩す。
税法では掛金の拠出の都度、損金に算入する。
上記の違いがあります。